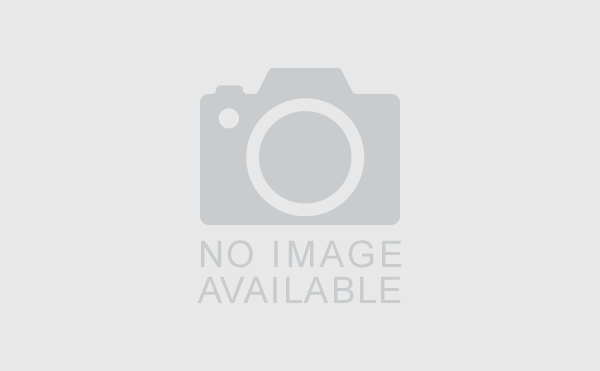会員が自院のホームページに歯周内科コンテンツを掲載する場合のガイドライン
1.位相差顕微鏡検査による検査が大切であることを記載する
2.リアルタイムPCR検査が重要であることを記載する
3.除菌後、歯石をとる必要があることを記載する
4.抗菌剤(抗生物質)と抗真菌剤を使用するという記述までで、ジスロマック、ハリゾン、ファンキゾンなどの薬剤名は載せない
5.歯周内科治療は保険外治療であることを必ず記載する
例)歯周内科治療は保険償還が確立していません。
下記の処置はすべて保険外治療になります。
(虫歯の治療や歯をかぶせるなどの治療は保険を適応することは可能です。)
[治療内容]
(1)位相差顕微鏡検査・リアルタイムPCR法による歯周病菌の検査診断の後の投薬
(2)位相差顕微鏡検査による除菌確認
(できれば菌叢変化の確認のためにリアルタイムPCR検査が望ましいが、最終検査時に行うことでも良い)
(3)歯周ポケット検査 歯石とり(病態によって回数は異なります)
(4)位相差顕微鏡検査・リアルタイムPCR検査・歯周ポケット検査(再評価)
(5)下記の文章を必ず入れる
歯周内科について (国際歯周内科学研究会HPより引用)
| 歯周内科治療は位相差顕微鏡検査・リアルタイムPCR検査で、お口の中に感染している細菌・真菌・原虫などを特定し、動画管理システムに記録しそれらの微生物に感受性の ある薬剤を選択し、微生物叢を非常に綺麗な状態に改善することで歯周病を内科的に治す治療方法です。
治療前の非常に汚れた微生物叢が治療後 は非常に短期間で綺麗に改善し、術前・術後の状態が一目瞭然に画像で示されるという利点があることが知られています。 また、はっきりと自覚 できる程、歯茎からの出血や排膿が短期間で改善されます。以前は、長時間歯磨きや外科治療によって1~2年の治療期間でそのような綺麗な微 生物叢を獲得していたのです。 微生物叢が改善されたら、歯石を除去します。その場合も、微生物叢が改善されていると、冷たいものがしみるというような症状が非常に少なく なることが知られています。 (なお、前歯においては短期間で歯茎が縮むので歯が伸びたような感覚が生じることがあります。そのような場合には残念ながら通常の治療では 元々骨が溶けている状態ですので改善は難しいようです。その場合は特殊な審美外科を行う必要があるかもしれません。 ) |
6.再発のリスクについて記載する
例) 歯周病は感染します
歯周病が治ったら再感染に 気をつけましょう!
回し飲み、回し食い、箸の使いまわし、キス、くしゃみなどで感染します。
家族から感染しまので、夫婦一緒に治療することをお勧めします。
7.ホームケアメインテナンスの大切さを記載する
例)お口の中を清潔に保つことが大切です
お口の中が清潔であれば歯周病菌が感染する可能性は低くなります。
毎日の歯磨きが大切です。歯科医院でブラッシングのコツを教えてもらいましょう。
毎日の歯磨きで歯周病菌が増えることを防ぐことができます。
自分で磨けない部分が必ずありますので、定期的に歯科医院での歯のクリーニングを受けましょう。
また、1年に一度は再感染の状態がないかリアルタイムPCR検査を受けることをお勧めいたします。